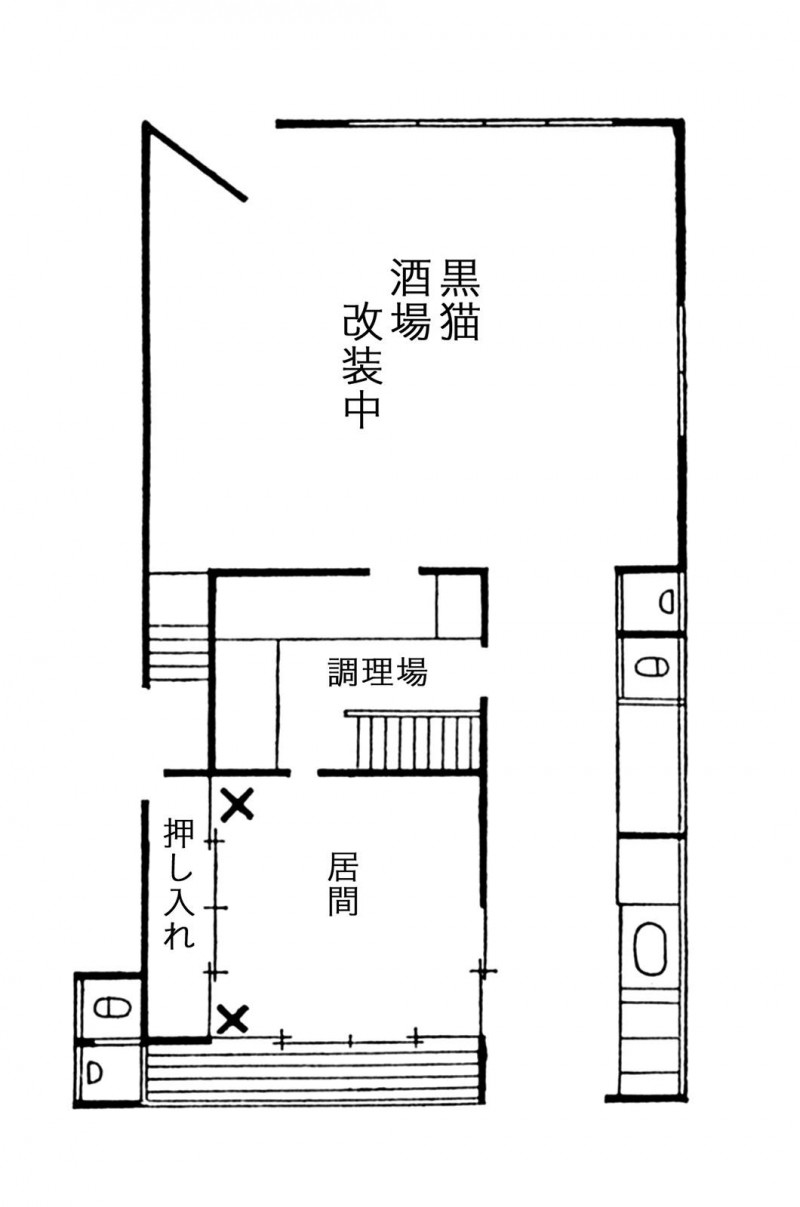「それについて、私たち、いまになって妙に思っているんですが、マダムは今月のはじめ
ごろから病気だといって、奥の六畳にひきこもったきり、一度も顔を見せませんでした。
ええ、その時分も、すこしへんだとは思いましたが、でも、それほど深く、気にとめてい
たわけではございません。しかし、いまになってかんがえてみると、あたしたち三人と
も、今月になって一度もマダムの顔を見ていないんです。おひまが出たときも、マダムに
挨拶をしようというと、マスターが、あれは病気だからいいとおっしゃるので……」
司法主任はそれをきくと、ふいと怪しい胸騒ぎをかんじた。その胸騒ぎの理由が、なに
によるのかはっきりつかめなかったが、なにかしら、えたいの知れぬドス黒い不安が、い
かすみのように、噴き出して来るかんじだった。
「しかし、マダムはいることはたしかにいたんだね」
「ええ、それはいました。あたしたちに顔を見せませんでしたけれど、御不浄へいく後ろ
姿などがときどき見えました。六畳のまえをとおると、向こう向きに寝ていて、本など読
んでいるのがよく見えました」
「いったい、マダムの病気というのはどういうことだね。それほどの病気で、医者を呼ぼ
うともしなかったのかね」
「いいえ、病気たって、そんな病気じゃなかったんです。マスターの話によると、悪い
ドーランにかぶれて、まるでお化けのような顔になった。だから、誰にも顔を見られたく
ないんだと、そういうお話でした。マダムはよくドーランにかぶれるので、去年も一度そ
んなことがあったのですが、今度はよほどひどかったのだと思います」
司法主任はまた怪しい胸騒ぎをかんじた。
「それで、マダムが顔を見せなくなったのは、いつごろからの事なんだね。はっきりした
日はわからないかね」
それについては、お君がこんなふうにこたえた。先月の二十八日、つまり二月のいちば
んおしまいの日は臨時休業だった。自分はその日、朝からひまをもらって、目黒の叔母の
家へ遊びにいって、一晩とまってかえった。するとマスターが、マダムは病気で寝ている
から、奥の六畳へちかよらないようにといった。それ以来、マダムの顔を見たことがな
い。……