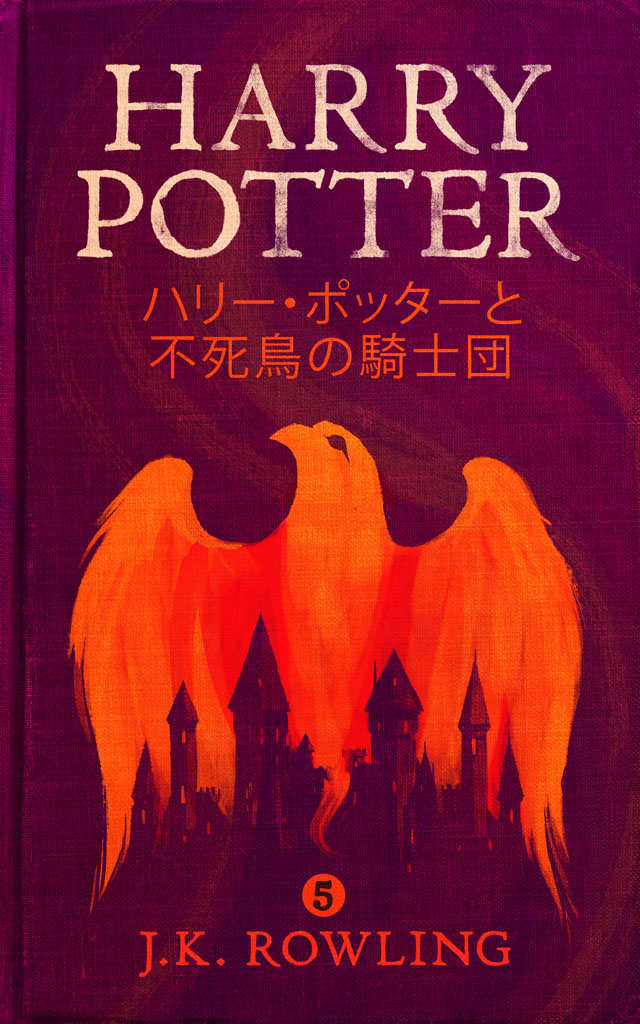
この夏一番の暑い日が暮れようとしていた。プリベット通りの角張かくばった大きな家々を、けだるい静けさが覆おおっていた。いつもならピカピカの車は、家の前の路ろ地じで埃ほこりをかぶったままだし、エメラルド色だった芝生しばふもカラカラになって黄ばんでいる――日ひ照でりのせいで、ホースで散さん水すいすることが禁止されたからだ。車を洗い上げたり芝生を刈かったりする、日ごろの趣味しゅみを奪うばわれたプリベット通りの住人は、日陰ひかげを求めて涼すずしい屋内に引きこもり、吹きもしない風を誘さそい込もうとばかり、窓を広々と開け放はなっていた。戸外に取り残されているのは、十代の少年がただ一人。四番地の庭の花壇かだんに、仰向あおむけに寝転んでいた。
痩やせた黒くろ髪かみの、メガネを掛かけた少年は、短い間にぐんと背丈せたけが伸びたようで、少し具合の悪そうなやつれた顔をしていた。汚いジーンズはボロボロ、色の褪あせたシャツはだぶだぶ、それにスニーカーの底が剥はがれかけていた。こんな格かっ好こうのハリー・ポッターが、ご近所のお気に召めすわけはない。なにしろ、みすぼらしいのは法律で罰ばっするべきだと考えている連中だ。しかし、この日のハリー・ポッターは、紫陽花あじさいの大きな茂みの陰かげに隠されて、道往みちゆく人の目にはまったく見えない。もし見つかるとすれば、バーノンおじさんとペチュニアおばさんが居い間まの窓から首を突き出し、真下の花壇を見下ろした場合だけだ。
いろいろ考え合わせると、ここに隠れるというアイデアは、我ながら天晴あっぱれとハリーは思った。熱い固い地面に寝転がるのは、たしかにあまり快かい適てきとは言えないが、ここなら、睨にらみつける誰かさんも、ニュースが聞こえなくなるほどの音で歯は噛がみしたり、意い地じ悪わるな質問をぶつけてくる誰かさんもいない。なにしろ、おじさん、おばさんと一いっ緒しょに居間でテレビを見ようとすると、必ずそういうことになるのだ。
ハリーのそんな思いが、羽を生はやして開あいている窓から飛び込んでいったかのように、突然バーノン・ダーズリーおじさんの声がした。

 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语



