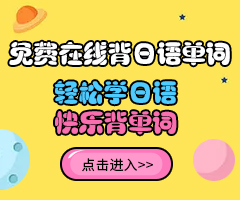「おい、大声を出すな。静かにしないと、拳銃の引金をひくぞ」
しかし、博士はそのままの姿勢で言った。
「あなたこそ静かにしてくれ。以前から研究していた新薬が、いま完成するところなのだ。すごい新薬だぞ……」
それから、おもむろにふりむく。
「……さあ、やっとできた。さて、ご用はなんでしょうか。どなたですか」
「のんきな人だね。いいか、おれは強盗なのだ。金をだせ」
「お気の毒だが、あなたはここへ来るのが早すぎた。この薬の発明が売れたあとだったら、まとまった金もあるのだが」
「なんだかすごい薬らしいが、どういうききめがあるのか」
「人生が楽しくなり、いい気分になり、夢のような生活と世界が現実のものとなる。その状態がいつまでもつづくのだ。あなたは、わざわざここへ乗りこんできた。この試作品はまだ一人前しかなく、あげるのは惜しいところだが、なんなら飲んでみますか」
博士の手の小さなびんには、緑色の液体が入っている。強盗は手をのばしかけたが、そこで考える。
「待てよ。それが強力な睡眠薬ということもありうる。まんまとその作戦にひっかかっては、ばかをみる」
「いらないのなら、ちょうどいい。わたしが飲むとしよう。自分で完成したのだから、最初に飲む感激は自分で味わいたいというものだ」
博士がびんに口を近づけるのを見て、強盗は小声で叫んだ。
「ちょっと待て」
「なんだ、気が変わって飲みたくなったのか。それだったら、飲ましてやるぞ。ほかに目ぼしいものは、ここにはないのだから」
博士がさし出したびんを強盗は手にし、眺めながら首をかしげた。
「意味ありげな薬であることは、たしかだな。しかし、いまの話や動作がみんな、真に迫った芝居だったということもありうるな。いい気になって飲み、しまったでは手おくれだし……」
ためらっている強盗から、博士はびんを取りかえして言う。
「うたぐり深い人だな。それなら、わたしが飲むことにするよ。そのあと、わたしをしばるなりなんなりし、金目のものが見つかったら、好きなだけ持っていくがいい」
博士はびんを口にあて、飲みはじめた。それを見て、強盗はすばやく取りあげた。
「どうやら、無害なものらしいな。よこせ、あとはおれが飲む……」
強盗は八分目ほど残っていたのを、みんな飲みほした。しかし、まもなく床に倒れ、かすれた声をあげた。
「からだがしびれて動けなくなった。いったい、どういうことなのだ。おまえは、なんともないのに」
「つまりだな、悪意にみちた精神状態のやつが飲むと、からだがしびれるのだ。善良な人間はなんともない。そういう効果があるのだ。これが普及したら、悪人はへり、夢のような生活と世界が現実のものとなるというわけだ……」
 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语