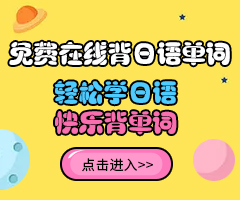さらに幾夜かがあった。中隊を出る時三日月であった月は、次第に大きさと光を増して行った。片側の嶺線からのぞき込むように現われると、谷を蔽う狭い空をさっさと越え、反対側の嶺線に隠れた。そして光だけ、長く対岸に残っていた。その整然たる宇宙的運行は、私を嘲けるように思われた。
片側の斜面が尽きて横谷が現われ、流れ出る水が落ち合って、河原を拡げていた。二つの水の間の三角の段丘に、椰子が群れていた。
葉柄の集まる梢に、実が小児の頭のように円みを並べていた。しかし幹は高く、衰えた私の体では攀じることは出来なかった。
葉扇は戛々と風に鳴った。私は根方の草に寝て眼をつぶり、その音だけを聞いていた。私は飢えを意識し、手に当る草を採ってその根を噛んだ。口中が痺れた。
夜、月が数々の葉末を剣のように光らした。空はそのあわいに藍色に澄んで、満月に近い月を、高く冷たく浮べていた。
私が命を断つべきは今と思われた。香わしい汁と甘い肉を持つ果実が頭上にあり、ここで私は徒らに飢えている。もし私がいつまでもここを去らないなら、やがて樹幹に醜くしがみついて、息絶えねばならぬかも知れぬ。まだ自分の行為を選ぶ力が残っているうちに、自分に出来ることをするべきではなかろうか。
輝く月光の行きわたった空が、新しい渇望をもって私の眼を吸い込んだ。私はこの感覚を知っていた。渇望は容易に「生への執着」と呼び得るものであるが、それが私の胸に起す感覚は、私の平穏な生活の過去において、既知のもののように思われた。幾度か私はこういう空を、違った緯度の下で、似通った気持で眺めたことがあった。
私は過去を探り、その時を確めようとした。記憶はなかなか来なかった。その時私は私を取り巻く椰子の樹群が、変貌しているのに気がついた。
それは私が過去の様々な時において、様々に愛した女達に似ていた。踊子のように、葉を差し上げた若い椰子は、私の愛を容れずに去った少女であった。重い葉扇を髪のように垂れて、暗い蔭を溜めている一樹は、私への愛のため不幸に落ちた齢進んだ女であった。誇らかに四方に葉を放射した一樹は、互いに愛し合いながら、その愛を自分に告白することを諾じないため、別れねばならなかった高慢な女であった。彼女達は今私の臨終を見届けるために、ここに現われたように思われた。
私は改めて彼女達と快楽を共にした瞬間を思い浮べた。或る女の腿は別の女の腕の太さしかなかった。しかし快楽の味わいは、死に近づいた私の肉体のメカニスムによって思い出に入り得ず、それに先立った渇望だけが思い出された。
私は月光の渡った空への渇望が、或る女が私が彼女を棄てる前に私を棄てた時、私の感じた渇望に似ていることに思い当った。私の手の届かないところへ去った女の心と体に、私は手が届かないという理由で、ひたすら焦れた。
して見れば今私があの空に焦れるのは、及び難いと私が知っているからであろう。私は自分が生きているため、生命に執着していると思っているが、実は私は既に死んでいるから、それに憧れるのではあるまいか。
この逆説的な結論は私を慰めた。私は微笑み、自分は既にこの世の人ではない、従って自ら殺すには当らない、と確信して眠りに落ちた。
 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语