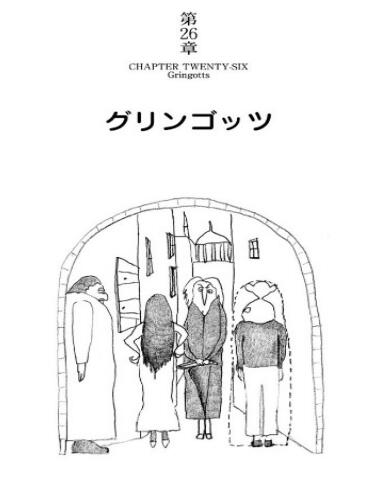
計画が立てられ、準備じゅんびは完了した。いちばん小さい寝室の、マントルピースの上に置かれた小瓶こびんには、長くて硬かたい黒くろ髪かみが一本――マルフォイの館で、ハーマイオニーの着ていたセーターからつまんだ毛だ――丸まって入っていた。
「それに、本人の杖つえを使うんだもの」ハリーは、鬼おに胡桃ぐるみの杖を顎あごでしゃくりながら言った。「かなり説得力があると思うよ」
ハーマイオニーは杖を取り上げながら、杖が刺さしたり噛かみついたりするのではないかと、怯おびえた顔をした。
「私、これ、いやだわ」ハーマイオニーが低い声で言った。「本当にいやよ。何もかもしっくり来ないの。私の思いどおりにならないわ……あの女の一部みたい」
ハリーは、自分がリンボクの杖を嫌ったとき、ハーマイオニーが一蹴いっしゅうしたことを思い出さずにはいられなかった。自分の杖と同じように機能しないのは気のせいにすぎないと主張し、練習あるのみだとハリーに説教したではないか。しかし、その言葉をそっくりそのままハーマイオニーに返すのは思いとどまった。グリンゴッツに押し入ろうとしているその前日に、ハーマイオニーの反感を買うのはまずいと感じたからだ。
「でも、あいつになりきるのには、役に立つかもしれないぜ」ロンが言った。「その杖が何をしたかを考えるんだ」
「だって、それこそが問題なのよ」ハーマイオニーが言った。「この杖が、ネビルのパパやママを拷ごう問もんしたんだし、ほかに何人を苦しめたかわからないでしょう この杖が、シリウスを殺したのよ」
ハリーは、そのことを考えていなかった。杖を見下ろすと、急に、へし折ってやりたいという残ざん忍にんな思いが突き上げてきた。脇わきの壁かべに立て掛かけてあるグリフィンドールの剣つるぎで、真っ二つにしてやりたかった。
「私の杖が懐なつかしいわ」
ハーマイオニーがみじめな声で言った。
「オリバンダーさんが、私にも新しいのを一本作ってくれてたらよかったのに」
オリバンダーはその日の朝、ルーナに新しい杖を送ってきていた。ルーナはいま裏うらの芝生に出て、遅い午後の太陽の光の中で杖の能力を試していた。「人さらい」に杖を取り上げられたディーンが、かなり憂ゆう鬱うつそうにルーナの練習を見つめていた。
ハリーは、ドラコ・マルフォイのものだったサンザシの杖を見下ろした。ハリーにとってはその杖が、少なくともハーマイオニーの杖と同じ程度には役に立つことがわかり、驚くとともにうれしかった。オリバンダーが三人に教えてくれた杖の技の秘密を思い出し、ハリーはハーマイオニーの問題が何なのかがわかるような気がした。ハーマイオニーは自分でベラトリックスから杖を奪うばったわけではないので、鬼胡桃の杖の忠ちゅう誠せい心しんを勝ち得ていないのだ。
 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语



