すりの源こう
ヘリコプターの操縦席のドアがひらかれ、待ちかまえていたおまわりさんが、そこへ近づくと、いきなり四十面相の手をとって、そとへひきずりおろしました。そして、手錠をはめようとしたときです。そのときまで、おとなしくしていた四十面相が、おそろしいいきおいで、おまわりさんの手をふりきって、いきなり、パッとうしろの群集の中へおどりこんだではありませんか。
「アッ!」とおどろいた警官たちが、そのほうへ、とびかかっていきました。
さいわい、四十面相がとびこんだのは、新聞記者たちの中でした。
「ちくしょう。逃がすものか。警官、ここにいますよ。早くつかまえてください。」
記者たちが、くちぐちにわめきながら、黒シャツすがたの四十面相を、前のほうへおしだしてくれました。
手錠をもった警官が、それにとびついていって、かちんと両手にはめてしまいました。
もうこんどは、逃げられません。十数名の警官にとりまかれて、四十面相はおとなしく、すぐむこうの警視庁のほうへ、ひったてられていくのでした。
まもなく四十面相は、警視庁の地下のしらべ室へ、つれこまれていました。正面には、捜査一課の係長のひとりである中村警部が、げんぜんと、いすにかけています。
中村警部は四十面相のために、たびたび出しぬかれているので、うらみかさなる相手です。
こんどこそは、もう逃がさないぞと、恐ろしい目でにらみつけていました。
そのよこに、明智探偵と小林少年が、ひかえていました。四十面相は、ふたりの警官にまもられて、その前に、しょんぼりと立っているのです。
「おい、四十面相、本名は遠藤平吉だな。きみは、せっかく脱獄したかと思ったら、もうつかまってしまったじゃないか。すこし、おいぼれたようだな。」
中村警部が、きみよさそうにいいました。
「エッ、四十面相? ……遠藤平吉?」
黒シャツの怪人は、ぼんやりした顔でふしぎそうにつぶやきました。
なんだかへんです。小林少年は、はやくも、それに気づいて、明智探偵のひざをつっつきました。そして、
「あいつ、どっか、顔がちがいますよ。ヘリコプターに乗っていたやつと、顔がちがってますよ。」とささやくのでした。
中村警部は、いまはじめて、近くで顔を見るのですから、そこまでは気がつきません。
「おい、遠藤、はっきり返事をしないか。きみは四十面相と名のる男だね。」
はげしくどなりつけますと、男は、きょとんとして、
「エッ、とんでもない。あっしゃ、そんなものじゃありませんよ。ひどいめにあったんです。日比谷の林の中で、三人の男につかまって、こんなものを着せられちまったんです。そして、むりやり、広っぱの人ごみの中へつれこまれ、おまわりさんの前へ、つき出されたんです。なにがなんだか、さっぱりわけがわかりませんや。」
黒シャツの男は、ふへいらしく、つぶやくのでした。
なんだか、ようすがおかしいのです。口のききかたも、四十面相とはまるでちがっています。
「そんなことをいってごまかそうとしたってその手にはのらないぞ。きさまが四十面相じゃないとでもいうのかッ。」
「アッ、そうだ。これを見ておくんなさい。その三人のやつが、しらべ室へいったら、これを見せるがいいといって、こんなものを……。」
男はそういって、黒シャツのポケットから、一まいの紙きれをとりだして、中村警部の前にさしだします。
うけとってみますと、その紙きれには、えんぴつで、こんなことが書いてありました。
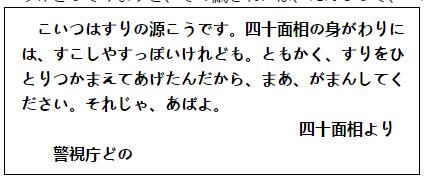
中村警部はそれを読むと、恐ろしい顔になって、黒シャツの男をにらみつけました。
「おまえ、源こうっていうのかッ。」
「へえ、あっしゃ、源こうですよ。」
男はへいきな顔で、すましています。
中村警部は、そばにいた警官に、なにか耳うちしました。すると、警官はすぐに、部屋のそとへでていきましたが、まもなくひとりの背広の人をつれてかえってきました。それは、すり係の刑事だったのです。
刑事は、部屋にはいって、黒シャツの男を一目見ると、
「アッ、おまえ、源こうだなッ。またやったのか。いったい、なんど、くらいこめばいいのだ。」
と、しかるようにいいました。そして、中村警部のほうにむきなおり、
「係長、こいつは前科七犯の有名なやつです。源こうにちがいありません。」
と、きっぱりいいきるのでした。
ああ、四十面相は、やっぱり魔法つかいでした。ヘリコプターの中にいたのは、まちがいのない四十面相でしたが、それがいつのまに、こんなすりに入れかわってしまったのでしょう。
明智探偵は、ちょっと、首をかしげて考えていましたが、すぐに魔法の種に気づきました。
「中村君、わかったよ。さっき四十面相がヘリコプターから、ひきずりおろされたとき、警官の手をふりきって、新聞記者のかたまっている中へ逃げこんだ。すると、記者の人たちが、こいつをとらえて、つきだしてくれたんだが、その瞬間に、人間の入れかえがおこなわれたんだ。
つまり、あの新聞記者たちは、にせもので、四十面相の部下が化けていたんだ。そして、まえもってこの源こうというすりをつかまえておいて、四十面相の身がわりにたてたのだ。顔がどこかにているし、あのさわぎのなかだから、警官たちも気づかなかったのだよ。なにしろ、四十面相とおなじ黒シャツすがただからね。この源こうに黒シャツを着せておいて、とっさに、人間のすりかえをやったのだよ。」
それにしても、四十面相の部下は、ヘリコプターが日比谷公園につくことを、どうして知っていたのでしょう。明智探偵はそこまでは気づきませんでしたが、読者諸君はごぞんじです。それは、空を飛んでいるとき、四十面相の部下のヘリコプターが、こちらとならんで飛んでいました。それにむかって、四十面相は懐中電灯の信号を、おくったのです。たぶん、モールス信号だったのでしょう。
四十面相の部下のヘリコプターは、その通信をうけると、すぐにどこかへ着陸して、電話で、なかまにこのことを知らせ、日比谷へさきまわりしているように、はからったのにちがいありません。
明智は、さらに説明をつけくわえました。
「あの黒山の人だかりだから、ほんものの四十面相は、どこかへ身をかくしてしまったんだ。記者にばけた部下たちが、オーバーかマントを用意していて、四十面相の黒シャツの上から着せてしまえば、夜のことだから、もうわかりっこないのだからね。」
「アッ、そうかッ。おい、新聞記者をよんできたまえ。みんなよんでくるんだ。」
中村警部がどなりました。ひとりの警官がとびだしていったかとおもうと、ぞろぞろと大ぜいの新聞記者が、しらべ室へはいってきました。
「公園のヘリコプターのそばで、この男をつきだして、警官にわたしてくれた人はいませんか。」
警部がたずねますと、記者たちは、たがいに顔を見あわせていましたが、その中のひとりがこたえました。
「いや、あれは新聞社のものじゃありませんよ。だれだかわからないが、ぼくたちのあいだに、六、七人、へんなやつがまじっていたのです。その連中が、こいつをつきだしたのです。」
「ふうん、ちゃんと用意をしていたんだな。それで、ほんものの四十面相が、どこへ逃げたか、きみたち気づきませんでしたか。」
警部がききますと、記者たちはびっくりして、
「エッ、じゃあ、こいつは四十面相じゃないのですか。」
「うん、すっかり黒星で、もうしわけないが、やられたんだ。あいつらは、この源こうというすりに、黒シャツを着せて、上からオーバーかなにかはおらせて、あそこへつれてきていたんだね。そして、とっさに人間のすりかえをやったんだ。」
中村警部は、すこし、めんぼくないような顔で説明しました。
なるほど、警視庁としては、大失策にちがいありません。しかし、明智探偵と小林少年は、それほど失望しているようにも見えないのはなぜでしょう……。ふたりは、まだあきらめていなかったからです。四十面相のほうに、奥の手があれば、こちらにも、ちゃんと、もうひとつ奥の手が用意してあったからです。
 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语



