真珠塔
そのあくる日、島田君は、学校で木下君にあうと、すぐに、ゆうべのできごとを話しました。
「いよいよ、へんだねえ。あいつは、きっと、きみのうちを、ねらっているんだよ。」
「ぼくを、ひどいめにあわせようというのかい。」
「いや、それなら、ぼくのほうを、さきにねらうよ。ぼくのおかげで、あいつ、デパートでひどいめにあったんだからね。そうじゃないよ。きみのうちには、きっと、あいつのほしいものがあるんだよ。」
「ウン、そう言えば、おとうさんも、なんだかそんなことを言ってたよ。しかし、ぼくには教えてくれないんだ。うちには、なんだか、あいつにねらわれるようなものがあるらしいんだけど。」
「それじゃ、きっと、そうなんだよ。ねえ、きみ、このことを黒川さんに知らせようじゃないか。東洋新聞の黒川さんさ。あの人なら、何かいいことを考えつくかもしれないぜ。」
「ああ、そうだ。それがいい。」
そこで、ふたりは先生にわけを話して、学校の電話で黒川記者を呼びだし、てみじかにいままでの出来事を知らせました。
「それじゃ、一度、きみのうちへおじゃますることにしよう。きょう夕方、おとうさんが帰られるころにね。そして、くわしい話を聞こう。」
黒川記者は、島田君のうちへの道順をたしかめて、電話をきりました。
その夕方、黒川記者はやくそくどおり、島田君のうちをたずねてきました。ちょうどおとうさんも帰られたところだったので、さっそく洋館の応接間にとおして、おとうさんと一郎君とで、かわるがわる、おとといからの出来事を話しました。
「フーン、やっぱり影をあらわしたのですね。影といえば、ぼくも、あいつの影には、ひどいめにあいましたよ。」
黒川記者は、いまいましそうに、つぎのような話をしました。
「二―三日まえのことです。天気のいい日でした。社の用事で、港区の屋敷町をあるいていた時です。両がわとも長いコンクリート塀のつづいた、さびしい場所でした。もう夕方のことで、赤い日ざしが、右がわのコンクリート塀を、いっぱいに照らして、あるいているぼくの影が、そこにうつっているのです。
ところが、ふと気がつくと、その影がいつのまにか、二つになっているじゃありませんか。オヤッと思って、あたりを見まわしても、だれもいないのです。人間はぼくひとり、影だけが二つあるのです。乱視というのは、物が二重になって見える病気ですが、まさか、ぼくがとつぜん乱視になるわけもありません。乱視でも、よほどひどくならなければ、影が二つに見えるなんてことはないのです。
ところが、一方の影は、よく見ると、帽子もかぶっていないし、服も着ていない。はだからしいのですね。だから、むろんぼくの影じゃありません。しかも、その影は、ぼくの影にくらべると、なんだかボーッと、かすんだように見える。スリガラスを、かべにうつしたような感じです。
ぼくはもういちど、あたりを見まわしました。やっぱり、だれもいません。そのくせ、影だけは、ぼくの影を追うように、あるいているのです。ぼくはこわくなってきて、足をはやめました。すると、あいても足をはやめる。立ちどまると、あいても、立ちどまる。
ぼくは思いきって、『だれだッ。』と、どなりつけてやりました。すると、どこからともなく、エヘヘヘヘヘヘヘヘと言う、いやーな笑い声がきこえてくるのです。ゾッとするような笑い声です。
ぼくが立ちどまっていると、そいつの影が、ぼくの正面にまわりました。つまり、影と影とが向きあったのです。そして、あいての影は、いきなり両手をひろげて、ぼくの影につかみかかってきました。いや、影ばかりではありません。ぼくのからだに、目に見えない手が、さわったのです。
じつにいやーな気持ちでした。ぼくはゾッとして、飛びのきました。そして、目に見えないやつを、力いっぱい、つきとばしておいて、死にものぐるいで、逃げだしたのです。もう、むがむちゅうでした。二百メートルもはしりつづけて、人通りの多い町までくると、やっと、ぼくの影は一つだけになりました。目に見えないやつは、どっかへ行ってしまったのです。
空気男は、ぼくをにくんでいるんですよ。しかし、いたずらをするだけです。ピストルや短刀は持っていないようです。きみが悪いけれど、どこかあいきょうのあるやつです。島田君にも、いたずらをしているだけかもしれませんよ。」
「そうだといいんですが、どうも、それだけじゃなさそうです。」
島田君のおとうさんは、心配らしく、声をひくめて言いました。
「すると、何か心あたりがあるんですか。」
「たった一つあるんです。わたしも、戦争後、いろいろなものを、なくしてしまいましたが、わたしのうちのたからと言ってもいいものが、一つだけ、たいせつに保存してあるのです。」
「フーン、あいつは、それをねらっていると、おっしゃるのですね。で、それは、いったい、どんなものです。」
「あなたは真珠塔というものを、ごぞんじですか。高さ二十センチぐらいの五重の塔で、それに真珠の玉がビッシリとはりつめてあるのです。何百ともしれぬ最上の真珠でできた、宝玉の塔なのです。この真珠塔は大正時代の大博覧会に、三重県の真珠王が出品したもので、なくなったわたしの父がそれを買いとったのです。そのころのねだんで十万円でした。今で言えば三千万円に近いものです。あの目に見えないやつは、宝石商から首飾りをぬすんだそうですが、あの首飾りの何十倍という、ねうちのあるものです。あいつは、それを知って、つけねらっているのじゃないかと思うのですよ。」
「その真珠塔はどこにおいてあるのですか。」
「だれも知らない場所にかくしてあります。わたしが真珠塔を持っていることは、世間でも知っているでしょうが、それがどこにあるかは、わたしと家内のほかは、だれも知りません。一郎も知らないのです。」
「このおうちの中ですか。」
「そうです。あなたには、いろいろ、お力をかりなければならないので、うちあけて、お話しますが、じつは、防空ごうを改造した地下室の中の金庫に入れてあるのです。」
「防空ごうですって? そんなところにおいては、あぶないじゃありませんか。」
「ところが、そうではないのです。防空ごうと言っても、厚いコンクリートでできた、がんじょうなものです。戦争中は庭からも、はいれるようになっていましたが、今では、その入り口をコンクリートでふさいで土をかぶせてしまいました。ですから、入り口はたった一つ、わたしの洋室の書斎にあるだけです。
書斎のゆかが、あげぶたになっているのです。それも、じゅうたんの下ですから、わたしでなければ、どこにあげぶたがあるかさえ、わかりません。そのあげぶたをあけて、ゆかの下にはいると、そこにもう一つ厚い鉄のとびらがあります。それはわたしの持っている特別のかぎでなければ、ひらきません。そこをはいって、だんだんをおりると、四畳ほどのコンクリートの部屋があり、そのまんなかに、金庫がすえてあるのです。金庫にも特別のかぎがいります。そのうえ、暗号錠ですから、かぎがあっても、暗号を知らなければ、ひらくことができないのです。
あれがねらわれているなと思ったとき、銀行の金庫にあずけることも考えてみました。むろん、銀行のほうが安全にはちがいないのです。しかし、銀行へ持ってゆく道がしんぱいです。あいては目に見えないやつですから、少しもゆだんがなりません。やっぱり、このまま地下室においたほうがいいように思うのです。」
「なるほど、それだけ、げんじゅうになっていれば、だいじょうぶでしょう。あなたの書斎のあげぶたを、とうぶんひらかないことですね。あいつは、目には見えないけれども、幽霊とはちがって、からだがあるのですから、入り口がしまっていれば、はいることはできません。しかし、あいつはなかなか知恵のあるやつですから、どんな計略をめぐらすかしれませんよ。うっかり、あいつの手にのらないことが、たいせつですね。」
話がここまで進んだとき、どこかでコトッと、かすかな音がしました。黒川記者は、ハッとしたようにおそろしい顔つきになって、いきなりイスから立ちあがって、ひらいたドアのほうへ、飛びついてゆきました。まるで気でもちがったようです。しかし、かれが入り口のところへかけつけたときには、ドアがひとりで動くように、大きな音をたてて、しまってしまいました。
黒川記者はそのとき、「ちくしょうッ。」とさけんで、まるで、だれかに、つきとばされたように、ヨロヨロとあとじさりましたが、なぜかまだ両手を前にだしたまま、何かをつかもうとしています。
見ると、かれの目の前の空間を、一枚の白い紙が、ヒラヒラと舞いおちていました。黒川記者はそれがゆかにおちるまでに、両手でつかみとって、じっと見ていましたが、また「ちくしょう。」とつぶやきながら、テーブルのところにたちもどり、島田君のおとうさんの前に、その紙きれをおきました。それには、鉛筆の大きな字で、こう書いてありました。
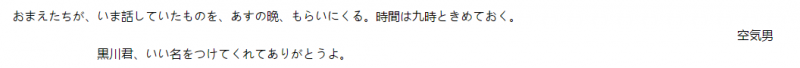
 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语



