双眼鏡
それよりすこしまえ、淡谷スミ子ちゃんは、園田ヨシ子ちゃんの顔を見たくなりました。
さっき、学校の帰りに、おもてでわかれてきたばかりですが、どうしたわけか、ヨシ子ちゃんにあいたくて、しかたがないのです。
それで、スミ子ちゃんは、双眼鏡を持って、二階の窓へいそぎました。
双眼鏡で、園田さんのうちの時計塔をのぞけば、ヨシ子ちゃんのすがたが見えるかもしれないと思ったからです。
二階の窓をあけて、双眼鏡を目にあて、ピントをあわせました。いつもヨシ子ちゃんと、ハンカチの信号で話をするのは、時計のすぐ下の、塔の四階の窓ですから、もしやヨシ子ちゃんが、そこへきていないかと思って、その窓へ、ピントをあわせたのです。
窓はしまっていました。ガラスのむこうにも、なにも見えません。
そのとき、双眼鏡のたまの上のほうに、なにか動いているものがありました。「オヤッ。」と思って、双眼鏡をそのほうにむけますと、そこには、じつにみょうなことがおこっていたのです。
大きな時計の文字ばんが、双眼鏡いっぱいにうつっています。その下のほうに、ふたつのまるい穴があいています。ねじをまく穴です。その穴から、ひょいと、人間の首が出ているではありませんか。
「アラッ、あれ、丈吉さんじゃないかしら。」
スミ子ちゃんは、びっくりして、ひとりごとをいいました。
「そうだわ、丈吉さんだわ……。アラッ、たいへん! 時計の針が、丈吉さんの首の上へさがってくる。アッ、あぶない。はやく、首をひっこめないと……。」
針は、じりッ、じりッと、おりてきました。丈吉君は、まだ気がつきません。
「アッ、首にさわった。首をおさえられてしまった。ああ、丈吉さん、やっと気がついて、首をひっこめようとしている。アラッ、ひっこめられないのかしら。ああ、だめだわ。丈吉さん、びっくりして、なにか叫んでいる。アッ、どうすればいいでしょう。だれか、はやく……。」
スミ子ちゃんは、きびんな少女でした。いきなり、双眼鏡をなげ出して、階段をかけおり、茶の間の電話機にとびつくと、受話器をはずして、園田さんの番号をまわしました。
× × × ×
大時計のほうでは、丈吉君の首のうしろへ、時計の針の鉄の板が、じりり、じりりと、くいいっていました。
さっきまでは、おしつけられるような感じだけでしたが、今は、ひどくいたみだしてきました。首の皮がきれて、たらたらと、血がながれているのです。
「いたいッ。ああ、死んじまう。はやく、助けてくれえ……、助けてくれえ……。」
丈吉君は、いたさにもがきながら、声をかぎりに叫びました。
しかし、だれも助けにきてくれるものはありません。おとうさんは、うちにいらっしゃるのですが、とても、そこまでは声がとどかないのです。塔の一階にいるヨシ子ちゃんにさえも、とどかないのです。
ああ、だれか、はやく助けなければ、丈吉君は死んでしまいます。神さま、はやく、だれかに知らせてください。そして、かわいそうな丈吉君を、助けてください!
× × × ×
その時、淡谷スミ子ちゃんの受話器へ、かわいい少女の声が出ました。
「ああ、あなた、ヨシ子ちゃんね。よかったわ。はやくよ……。」
「え、なにがはやくなの? あなただれ?」
ヨシ子ちゃんは、なにも知らないので、いやにおちついています。
「わたしよ。スミ子よ。たいへんだわ。あなたのおにいさんが、死にかけている。はやくよ。」
「エッ、死にかけているって? どこで?」
「時計塔よ。時計の文字ばんに、ふたつ穴があいているでしょう。その穴から首を出して、時計の針にはさまれているのよ。はやく、はやくしないと、首が切れちゃうわ。」
がちゃんと、ヨシ子ちゃんが、受話器をおく音がしました。
「はやくよ。わかって……?」
なんの答えもありません。ヨシ子ちゃんは、にいさんを助けるために、おとうさんのところへ、とんでいったのにちがいありません。
でも、スミ子ちゃんは、心配でしかたがありませんので、また、二階へかけのぼって、双眼鏡を目にあてるのでした。
× × × ×
丈吉君は、あぶないところで助かりました。
ヨシ子ちゃんがおとうさんに知らせ、おとうさんが、時計塔にかけのぼって、歯車をぎゃくに回したからです。
助けだされた丈吉君は、気をうしなって、ぐったりとしていましたが、おとうさんにからだをゆすぶられると、やっと目をひらきました。
「しっかりしろ。きずは、たいしたことないぞ。」
おとうさんが、おちついた声でいいますと、丈吉君は、いきなりおとうさんに、しがみついてきました。さすがに勇敢な丈吉君も、時計の針のごうもんは、よほどこわかったものとみえます。
しかし、きずは、ほんとうにたいしたこともなかったのです。首のうしろから血がながれていましたけれど、大きな血管はぶじでしたから、お医者さまに、薬をつけてもらえば、じきになおってしまうでしょう。
丈吉君とヨシ子ちゃんが、赤い道化師のことをいいましたので、おとうさんは、書生をよんで、ふたりで機械室をしらべてみましたが、もう道化師のすがたは、どこにもありませんでした。
「オヤッ、こんなものが、歯車のあいだに、ひっかかっていましたよ。」
書生が、一まいの紙きれをさしだしました。園田さんが、手にとってみますと、その紙には、えんぴつで、こんなことが書いてあったのです。
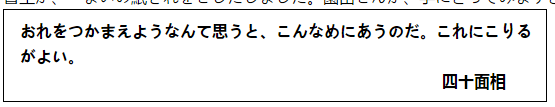
ああ、やっぱり赤い道化師は、四十面相の変装だったのです。
それにしても、かれはいったい、どこへ逃げてしまったのでしょう?
機械室は、三方の文字ばんに、つごう、六つのまるい穴があいているばかりで、窓というものがありません。まるい穴からは、とても、おとなのからだは出られないのですから、まったく、逃げ道はないはずです。
塔の階段をおりたとすれば、だれかに見つかっているはずです。園田さんのうちには、書生や女中が大ぜいいますから、だれにもしられないように、逃げだすなんて考えられないことです。
それから、丈吉君をひと間に寝かせて、お医者さまをよび、手あてをしてもらいましたが、首のきずは、四、五日でなおるというお話でした。
丈吉君が、ぶじに助かったのは、淡谷スミ子ちゃんが、すばやく電話で知らせてくれたおかげですから、おとうさんも、おかあさんも、たいへんおよろこびになって、すぐ淡谷さんのうちへ、おれいにいかれましたが、ヨシ子ちゃんは、その案内やくをつとめたのでした。
それにしても、道化師に化けた四十面相は、園田さんのうちにしのびこんで、いったい、なにをたくらんでいるのでしょう。
 英语
英语 韩语
韩语 法语
法语 德语
德语 西班牙语
西班牙语 意大利语
意大利语 阿拉伯语
阿拉伯语 葡萄牙语
葡萄牙语 越南语
越南语 俄语
俄语 芬兰语
芬兰语 泰语
泰语 丹麦语
丹麦语 对外汉语
对外汉语



